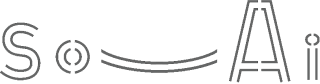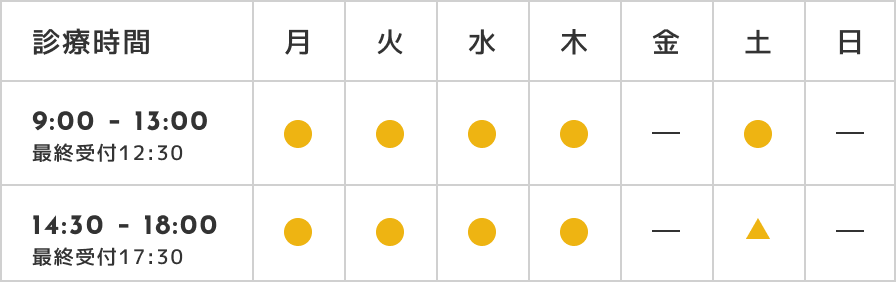小児矯正の保険適用は可能?条件と費用を安くする方法を詳しく解説

小児矯正は、お子さんの歯並びや噛み合わせを整えるために必要な治療ですが、その費用が家計に与える負担を心配される親御さんも多いのではないでしょうか。特に、保険が適用されるかどうかは、治療を始める上で重要なポイントの一つです。
小児矯正は多くの場合、自由診療となり保険適用外となることが一般的ですが、特定の条件を満たす場合に限り保険が適用されるケースがあります。本記事では、小児矯正で保険適用される条件や具体的なケースについて詳しく解説します。さらに、保険適用されない場合でも、治療費を抑えるための具体的な方法についてもご紹介します。
お子さんにとって最適な治療を、無理のない範囲で受けさせたいと考える親御さんに向けて、この記事が判断材料として役立つ内容になれば幸いです。ぜひ最後までご覧いただき、お子さんの矯正治療をスムーズに進めるための参考にしてください。
目次
小児矯正で保険適用される3つのケース
小児矯正は、多くの場合保険適用外となりますが、特定の条件を満たす場合には保険が適用されるケースがあります。日本矯正歯科学会によると、小児矯正で保険が適用されるのは以下の3つの条件を満たす場合のみです。
厚生労働大臣が定める遺伝性疾患による咬合異常
唇顎口蓋裂や鎖骨頭蓋骨異形成など、特定の遺伝性疾患が原因で咬合異常が生じている場合、保険が適用されます。このような疾患は60種類以上がリストアップされており、これらに該当する場合は治療が保険適用の対象となります。矯正歯科治療が必要な場合は、該当疾患について事前に確認しておきましょう。
参考:公益社団法人 日本矯正歯科学会 矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは
永久歯3歯以上の萌出不全
永久歯の中でも前歯や小臼歯が3本以上萌出しない(生えてこない)状態に該当する場合、保険が適用される可能性があります。ただし、この条件には「歯茎を切開して歯を生えさせる外科的処置」が必要であるという制限があります。単に生え揃わないだけでは保険適用外となるため、歯科医師の診断を受けることが重要です。
顎変形症による手術前後の矯正治療
上顎や下顎の形、大きさ、位置が異常で、噛み合わせに支障がある顎変形症の場合、手術を伴う矯正治療に限り保険が適用されます。この場合、手術前後の矯正治療を含むすべての治療費が保険適用の対象となります。ただし、顎変形症を外科的な手術をせずに歯列矯正だけで治療する場合は、保険適用外となるため注意が必要です。
小児矯正で保険適用に年齢制限はある?
小児矯正において、保険適用に年齢制限はありません。子どもや大人に関わらず、特定の条件を満たしている場合に限り、保険適用が認められます。国が定めた疾患や症例が原因で咬合不全が生じている場合、年齢にかかわらず保険が適用されるのが特徴です。
たとえば、顎変形症や先天的な病気(唇顎口蓋裂など)に起因する咬合異常は、小児矯正でも成人矯正でも保険適用となることがあります。一方で、一般的な歯列矯正の場合、保険適用はされないため注意が必要です。
ただし、年齢が若い段階での矯正治療には大きなメリットがあります。成長期の子どもは顎や歯の発育が進行中のため、外科的処置が必要な場合でも早期の治療で全身の発育をサポートできる可能性があります。そのため、特定の症例においては、小児矯正の方が適用の対象となりやすいケースもあります。
また、保険適用の有無を判断するためには、専門の歯科医師による診断が不可欠です。外科的処置を含む治療が必要な場合には、子どもの全身の健康状態や発育の影響も考慮されます。矯正治療を始めるタイミングについては、早めに歯科医院で相談することをおすすめします。
結論として、小児矯正の保険適用には年齢制限はありませんが、適用されるかどうかは症例の内容に左右されます。お子さんの治療が保険適用となる可能性があるかどうか、専門家に相談してみましょう。
小児矯正におすすめの保険会社【保険適用の場合のみ】
小児矯正の治療費が保険適用となる場合、医療保険や共済保険を活用して、費用負担をさらに軽減できる可能性があります。ここでは、小児矯正に関連して検討すべきおすすめの保険会社を紹介します。保険選びの際に、適用条件や補償内容を十分に理解しておくことが重要です。
コープ共済
コープ共済は、比較的手軽に加入できる共済保険で、小児矯正の費用補助が受けられる場合があります。ただし、保険金が下りるのは、矯正治療が生活に支障をきたす疾患(例:顎変形症や唇顎口蓋裂など)に関連している場合に限られます。見た目の改善や予防目的で行う矯正治療は対象外となることが多いので注意が必要です。
コープ共済を利用する際は、事前に歯科医師に診断を依頼し、保険金の申請が可能かどうかを確認しましょう。また、補償内容が自治体やプランによって異なるため、具体的な条件については加入時にしっかり確認してください。
県民共済
県民共済も、小児矯正に関連した補償が受けられる可能性がある保険の一つです。特に、特定の疾患に伴う外科的処置が必要な場合に適用されることがあります。ただし、補償条件は都道府県ごとに異なるため、居住地の共済内容を詳しく調べることが重要です。
県民共済は月額保険料が比較的安価で、手続きも簡単なため、多くの家庭で利用されています。しかし、こちらもコープ共済と同様、見た目の改善目的や予防的な矯正治療は補償対象外となることが一般的です。
保険適用されない場合の小児矯正|自費治療の費用を抑える方法
ここまで保険適用される前提でお話してきました。しかし、小児矯正の多くが保険適用外となり、治療費用の全額をお支払いしていただく必要があります。
そのため、できるだけ費用を抑えたり、月支払いに変更し、家計への負担を軽減する方向で考えなければなりません。矯正治療は高額になりがちですが、以下の方法を検討することで、家計の負担を軽減することが可能です。それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、最適な方法を見つけてください。
1期治療から矯正を始める
1期治療とは、永久歯が生え揃っていない成長期の子どもに対して、顎の骨格を整えることを目的とした矯正治療です。この時期に治療を始めることで、歯が正しい位置に生えるための土台を作り、将来的な矯正治療をスムーズに進めることが可能です。
1期治療を行わずに、永久歯が生え揃った後に矯正治療(2期治療)を行うこともできますが、1期治療を行うことで以下のようなメリットがあります。
- トータルの治療費が抑えられる可能性がある
- 治療が早く完了する可能性がある
- 抜歯のリスクが減る
また、1期治療で十分な成果が得られた場合、2期治療を必要としない場合もあります。このようなケースでは、治療費をさらに抑えることが可能です。一方で、適切な治療開始時期を逃すと、後に複雑な治療が必要になる場合もあるため、早めに専門医に相談することをおすすめします。
医療費控除の活用
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定の基準を超えた場合に適用される制度で、高額な矯正治療費を軽減する有効な手段です。この制度を活用することで、所得税が減額され、支払った治療費の一部が還付金として戻ってきます。
医療費控除の対象額は、「1年間の医療費(上限200万円)から、保険金で補填される金額と10万円または所得の5%(どちらか少ない額)を引いた額」として計算されます。たとえば、年間医療費が100万円、所得が500万円の場合、控除額は(100万円 – 10万円)=90万円となり、所得税率20%を適用して18万円が還付されます。このように、所得が高いほど還付額も大きくなる仕組みです。
控除を受けるには、領収書や通院交通費の記録を保管し、確定申告時に医療費控除の明細書を提出する必要があります。確定申告はe-Taxを利用するか、税務署で直接行うことが可能です。さらに、この制度は過去5年分に遡って申請することもできます。申請を忘れていた場合でも、領収書や必要書類を確認すれば、後から申請して還付を受けることができます。
ただし、矯正治療が美容目的である場合や、治療目的が見た目の改善のみである場合は医療費控除の対象外となる可能性があるため注意が必要です。治療が噛み合わせや咀嚼機能の改善を目的としている場合は、控除対象になる可能性が高いので、事前に医師に確認すると良いでしょう。
医療費控除は家族全体で支払った医療費を合算することが可能なため、世帯単位で申請することで控除額が増える場合もあります。
関連記事
小児矯正と医療費控除|対象費用から申請方法まで完全解説
分割払いやデンタルローンの活用で一時的な家計への負担を抑える
矯正治療は高額になりがちですが、分割払いの利用やデンタルローンを活用することで、一時的な家計への負担を抑えることができます。
分割払いは、歯科医院が独自に提供する支払いプランであることが多く、無利子や低金利で利用できる場合があります。たとえば、治療費を数回に分けて支払うことで、一度にまとまった金額を用意する必要がなくなります。また、治療期間中に支払いを済ませる形式が一般的で、柔軟な対応が可能です。分割回数や条件は医院によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
一方、デンタルローンは、矯正治療を目的としたローン商品で、専門の金融機関が提供しています。このローンを利用することで、一時的な家計への負担を軽減することができます。デンタルローンは通常、銀行ローンよりも金利が低く設定されているため、月々の支払い負担も少なく済みます。ただし、ローンの利用には審査が必要で、場合によっては融資が難しいケースもあるため、早めに申請手続きを進めることをおすすめします。
これらの支払い方法を選択する際には、総支払額を確認し、利息が発生する場合にはそのコストも計算に入れて検討することが重要です。計画的に支払える方法を選ぶことで、安心して治療を進めることができます。
モニター募集をしている医院に依頼する
矯正治療の費用を抑えたい場合、モニター募集をしている歯科医院を利用する方法があります。モニター募集とは、治療の症例写真の提供やアンケート回答、SNSへの口コミ投稿などを条件に、通常の治療費よりも安く矯正治療を受けられる仕組みです。特に費用面での負担を軽減したい家庭にとって魅力的な選択肢と言えるでしょう。
ただし、モニター募集を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、治療方法が医院によって指定されることが多く、自分が希望する治療方法を選べない場合があります。たとえば、マウスピース矯正を希望していたのに、医院側の指定でワイヤー矯正が適用されることもあるため、事前に確認することが大切です。
また、モニター治療にはリスクも伴います。2023年には、モニター商法を利用したマウスピース矯正で問題が発生し、集団訴訟に発展したケースも報告されています。途中で治療が中断せざるを得なくなった場合、元々なかった症状(出っ歯やすきっ歯など)が新たに生じるリスクがあるのです。このような場合、治療を再開するには他の医院で正規の治療費を支払い、改めて治療を始める必要があります。
モニター募集を利用する際は、治療内容や条件をしっかりと確認し、医院の信頼性を見極めることが重要です。また、契約書や同意書を注意深く確認し、リスクや費用の全体像を理解した上で決断するようにしましょう。
費用を抑えられるメリットはありますが、リスクとメリットを天秤にかけ、自分に合った選択をすることが大切です。安心して治療を受けるためにも、信頼できる歯科医院を選び、納得した上でモニター治療を利用しましょう。
矯正装置の種類を安価なもので検討する
小児矯正で使用される矯正装置には、ワイヤー矯正やマウスピース矯正など、さまざまな種類があります。矯正装置を選ぶ際、審美性を重視して目立ちにくい装置を選ぶと、費用が高額になることが一般的です。一方で、目立つ装置や標準的な装置を選ぶことで、治療費を抑えることが可能です。
たとえば、ワイヤー矯正では、歯の表面に装着するメタルブラケットが最も安価でありながら、治療効果が高い選択肢とされています。一方、歯の裏側に装着するリンガルブラケットや、取り外し可能なマウスピース矯正(インビザラインなど)は、見た目に配慮されていますが、費用が高くなる傾向があります。
矯正装置の選択は、費用だけでなく治療の効果やお子さんの生活スタイルにも影響を与えるため、慎重な判断が必要です。たとえば、マウスピース矯正は取り外しが可能なため食事や歯磨きがしやすい一方で、1日20時間以上装着する必要があり、装着時間が守れないと治療計画が遅れる可能性があります。
費用を抑えつつ、最適な装置を選ぶためには、担当の歯科医師に相談し、治療目的や予算に応じた選択肢を検討することが重要です。また、装置の選択だけでなく、保定期間や追加費用についても事前に確認しておくと安心です。
矯正装置は種類が多いため、全体のコストと治療計画を踏まえたうえで選択することが大切です。医師としっかり相談し、費用と治療効果のバランスが取れた装置を選ぶことで、安心して治療を進めることができるでしょう。
部分矯正で治療できるかを検討する
部分矯正は、矯正治療の中でも比較的費用を抑えることができる方法です。治療範囲を特定の歯やエリアに限定することで、全体矯正に比べて短期間で治療を終えることができるため、費用や時間の負担を軽減できます。
部分矯正が適しているのは、歯並び全体に大きな問題がなく、一部の歯の位置を調整するだけで十分な場合です。たとえば、前歯の軽度の歯列不正や、噛み合わせに特定の問題がある場合には部分矯正が効果的です。治療費は全体矯正の約半分から3分の1程度になることが一般的です。
しかし、部分矯正には限界もあります。治療範囲が限定されるため、顎の骨格や噛み合わせ全体に問題がある場合には適用できません。また、見た目だけを改善した結果、噛み合わせに問題が残る可能性もあります。そのため、部分矯正を希望する場合でも、歯科医師による詳細な診断が必要です。
部分矯正を選択する際には、治療のメリットとデメリットを十分に理解し、長期的な視点で判断することが重要です。費用面での負担を抑えることができる反面、全体的な機能改善が必要な場合には、全体矯正の方が適していることも多いです。
治療方法の選択は、患者さん一人ひとりの状態に応じて異なります。信頼できる歯科医師と相談し、自分に最適な治療方法を見つけることが、効果的かつ無駄のない治療への第一歩となります。
まとめ
小児矯正は、お子さんの歯並びや噛み合わせを整えるために重要な治療ですが、費用や保険適用の有無が親御さんにとって大きな関心事です。この記事では、小児矯正で保険が適用される条件や適用外の場合の費用を抑える方法について詳しく解説しました。
まず、小児矯正が保険適用となるのは特定の条件を満たす場合に限られます。例えば、遺伝性疾患や顎変形症による治療、永久歯3歯以上の萌出不全などが該当します。ただし、保険適用には専門的な診断が必要であり、早めの相談が重要です。また、保険適用には年齢制限がないため、大人や子どもを問わず条件に該当すれば適用されます。
一方で、保険が適用されない場合でも、治療費を抑えるための選択肢があります。1期治療から矯正を始めることでトータル費用を削減したり、医療費控除を活用することで実質的な負担を軽減したりする方法があります。また、分割払いやデンタルローンの利用、モニター募集への参加なども検討できます。さらに、矯正装置の種類を安価なものにしたり、部分矯正を選ぶことで費用を抑えることが可能です。
これらの方法を活用することで、家計に無理のない範囲で小児矯正を進めることができます。お子さんの将来の健康と笑顔のために、専門医としっかり相談し、最適な治療計画を立てることが大切です。